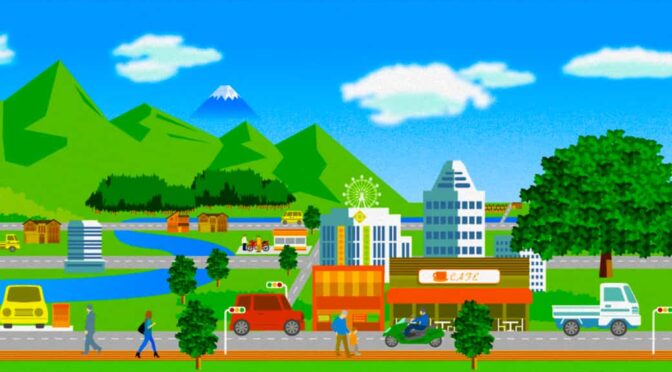一般社団法人全国軽自動車協会連合会 ( 全軽自協 / 会長:赤間俊一、略称:全軽自協) は8月21日、令和6( 2024 )年12月末現在の世帯当たり軽四輪車の普及台数の集計結果を明らかにした。
それによるとその数値は、100世帯に54.46台と、昨年の54.49台から3年振りの減少となった。
より具体的には、世帯当たりの普及台数は、総務省調べの「住民基本台帳に基づく世帯数」( 令和7年1月1日現在 )と国土交通省調べの「自動車保有車両数」( 令和6年12月末現在 )をもとに算出したところ、世帯数( 外国人世帯数を除く )は5,895万5,700世帯( 前年同期比21万6,812世帯増 )、軽四輪車の保有台数は3,210万8,227台( 同10万3,821台増 )となっていた。
つまり軽四輪車の世帯当たり普及台数は、昭和52( 1977 )年から平成30( 2018 )年まで43年連続で伸びていた。
その後の令和元( 2019 )年以降、軽四輪車の保有台数は、継続して増加したものの、世帯数の増加率が軽四輪車の保有増加率を上回ったため、微減する状況が令和3( 2021 )年まで続いていた。
それが令和4( 2022 )年に再び軽四輪車の保有増加率が上回り、令和5( 2023 )年まで2年連続で増加していたのが、これが3年振りの減少に転じたことになるという。
ちなみに、令和6( 2024 )年12月末現在の普及率を都道府県別にみると、世帯当たり普及率が高い順に、(1)長野県、(2)鳥取県、(3)島根県、(4)佐賀県、(5)山形県となり、1位から5位まで全て昨年と同じ県が並び、長野県は6年連続で1位となった。
「100世帯に100台(1世帯に1台 )以上の普及」は、4県( 前年と同数 )、「100世帯に90台以上の普及」は、13県( 前年と同数 )、「100世帯に80台以上の普及」は28県( 前年と同数 )、「100世帯に70台以上の普及」は34県( 前年と同数 )、「100世帯に60台以上の普及」は37県( 前年と同数 )だった。
反対に普及率の低い順では、(1)東京都、(2)神奈川県、(3)大阪府、(4)千葉県、(5)埼玉県の各都府県となり、「100世帯に50台以下の普及」は8都道府県(前年と同数)となっている。