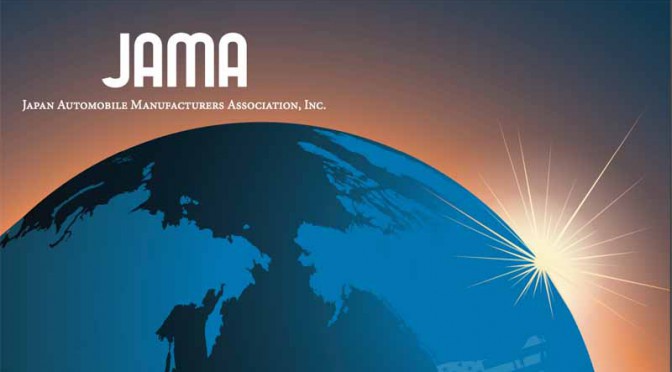一般社団法人 日本自動車工業会( 所在地:東京都港区、会長:片山 正則 )は4月15日、2024年度に実施した『普通トラック市場動向調査』と『小型・軽トラック市場動向調査』の結果をまとめた上で、記者説明会を開くなどで、その概要を明らかにした。
当該調査は、普通トラックの保有・購入・使用実態、輸送ニーズの変化と対応や、物流を取巻く市場環境の変化を時系列的に捉え、隔年でアンケートを実施しているもの。
荷主調査は、4年前の2020年度に実施したヒアリングをより深める形で、各業界の荷主等の企業に協力を得て実施した。また、時系列での分析と併せて以下のドライバー環境などの把握も行った。
– 2024年問題(ドライバーの時間外労働の上限規制)
– 環境意識と次世代環境車
– 安全に対する意識
– 物流DX
————————————————–
普通トラック市場動向の調査概要は以下の通り
————————————————–
ユーザー調査より
▷経営状況
運輸業、自家用とも経営状況が好転している事業所は増えているが、全体の中では少数派である。
エネルギー価格の高止まりも経営を圧迫しており、本格的な回復には至っていない様子がうかがえる。
▷需要動向
国内全体の輸送総量は、新型コロナ後に一時的に回復を見せたが、直近では減少傾向にある。
だが、運輸業の大規模事業所、経営が好調な事業所でのトラック購入意向は高い。
▷2024年問題(ドライバーの時間外労働の上限規制)
ドライバー不足は、特に運輸業で強まっている。その対策として、運輸業では給与面や運転時間面での改善に努めており、荷主に対しても運賃の適正化や時間の効率化への協力を求めている。
▷環境意識と次世代環境車
エコドライブ、低燃費車両はユーザー・荷主ともにニーズあり。カーボンニュートラル対応となるハイブリッド車導入意向は、運輸業の中型トラックが2割弱で前回と同程度。
▷安全に対する意識
運輸業では、対面点呼や酒気帯び確認等、健康管理を中心としたドライバー管理が交通事故防止安全対策の上位に。自家用では乗務前の酒気帯び確認実施率が大幅に増加。
自動運転走行機能・隊列走行については、「ドライバー不足解消」「事故の減少」効果を認識しつつも、導入意向は3割程度で前回並み。
▷物流DX
物流DX対応については、今後取り組む施策としての認識は徐々に高まりつつあるが、実際に取り組むとなると他の懸案事項が優先され、物流DXへの取り組みを身近に感じている事業所は限られている状況がうかがえる。
————————————————–
荷主等ヒアリングより
各社では、トラックドライバー対応、事前出荷情報(ASN : Advanced Shipping Notice)や倉庫・現場管理、環境車両・カーボンニュートラル等の領域で、自社及び連携による幅広い取り組みが進められている。
今後は、こうした物流最適化の取り組みを支える各ステークホルダーにおける更なる取り組みの加速が求められる。
————————————————–
報告書は下記URLリンクの自工会WEBサイトにも掲載されている。
http://www.jama.or.jp/library/invest_analysis/![]()
以下参考<2024年度普通トラック市場調査の概要>
————————————————–
1.調査実施概要
————————————————–
▷ユーザー調査
調査地域:全国
調査対象:普通トラック保有事業所(軽・小型トラック併有事業所を含む)
調査方法:郵送法
サンプリング:
運輸業:企業・事業所リストより運輸業該当企業としてランダムに抽出/有効回収数:1,005サンプル
建設業、製造業、卸・小売業:普通トラック保有企業リストより抽出/有効回収数:319サンプル
調査実施期間:2024年8月下旬~10月上旬
▷荷主等ヒアリング
調査対象:大手荷主等企業
調査業種:製造業、建設業、物流企業、卸・小売業
実施先:普通トラック分科会各社の紹介による4社
調査方法:訪問でのヒアリング
回答者:物流部門の担当者等
調査時期:2024年9月下旬~12月上旬
————————————————–
2.調査結果概要
————————————————–
(1)ユーザー調査
[経営状況]
運輸業、自家用とも経営状況が好転している事業所は増えているが、全体の中では少数派である。エネルギー価格の高止まりも経営を圧迫しており、本格的な回復には至っていない様子がうかがえる。
今回の調査結果では、最近の経営状況が『好転』した事業所は、運輸業では前回(22年度)の15%から24%に増加し、自家用では35%と前々回(18年度)からの増加傾向が続いている。
2年前と比べた荷扱量水準は、運輸業平均で前回93.0%から96.7%に増加しているが、自家用は99.2%から97.9%に微減している。
現在のトラック稼働状況の『繁忙』の割合は、運輸業では31%から34%に増加しているが、自家用は38%から28%に減少している。
世界的な社会情勢等の影響を受け、燃料費は前回よりも割合は低下しているが、引き続き運輸業2位、自家用で1位。燃料価格も下がっていないので、24年問題とともに引き続き、経営上の課題としては大きいとみられる。
————————————————–
[需要動向]
国内全体の輸送総量は、新型コロナ後に一時的に回復を見せたが、直近では減少傾向にある。
だが、運輸業の大規模事業所、経営が好調な事業所でのトラック購入意向は高い。
国土交通省の交通関連の統計資料*によると、20年度に新型コロナの影響により大きく減少した国内貨物の輸送量は、輸送トン数については21年度に一時的に増加するも22年度以降は減少傾向が続く。新型コロナ後の増加していた輸送トンキロも23年度は減少した。
トラックは、輸送トン数は国内貨物と傾向は同じだが、輸送トンキロは新型コロナ以降増加が続いている。構成は、輸送トン数、輸送トンキロとも10年前と似た状況にある。
普通トラックの新車販売台数*は、19年からは減少傾向となり、特に22年は5.7万台と過去10年間で最低台数となったが、23年は6.7万台、24年は7.3万台と回復している。一方、普通トラック保有台数は、近年増加傾向が続いていたが、24年3月の推計値では減少に転じている。
運輸業での現保有車の購入形態は、「代替」が前回同様6割台で過半数を占める。
保有台数の増減状況は、この2年間で保有台数を増やした事業所、今後5年間で購入意向のある事業所の割合は、運輸業・自家用とも前回と同程度で、全体としては大きな動きはみられない。
だが、運輸業の中でトラック保有台数が多い事業所や経営状況が好転した事業所では、直近2年間で事業所全体での保有台数が「増えている」割合や今後5年間の購入意向割合が他と比べて高い。
注:
交通関連の統計資料は「自動車輸送統計年報」「鉄道輸送統計年報」「内航船舶輸送統計年報」「航空輸送統計年報」。
新車需要および新車登録台数は、暦年(1月~12月)の台数について表記。
————————————————–
[2024年問題(ドライバーの時間外労働の上限規制)]
ドライバー不足は、特に運輸業で強まっている。その対策として、運輸業では給与面や運転時間面での改善に努めており、荷主に対しても運賃の適正化や時間の効率化への協力を求めている。
ドライバーの不足状況(かなり+やや)をみると、自家用は前回21%から19%とやや減少しているが、運輸業では前回39%から45%に増加しており、運輸業のドライバー不足の切迫感は強まっている。
運行状況をみると、運輸業では、1回あたりの平均運行距離と月間走行距離は減少しており、ドライバーの時間外労働の上限規則が走行距離に影響を与えている様子がうかがえる。また、高速道道路の利用距離割合平均も着実に増加している。
上記に対する運輸業の対策は、「荷主への運賃値上げの交渉」「高速道路の利用を増やす」「ドライバー給与の引き上げ」が上位に挙がっており、ドライバー確保に向けて給与面と運転時間面の改善に努めている様子がうかがえる。
運輸業では、10トンクラスの保有率が増加傾向にあり、大型免許で運転できるトラックの保有を増やした比率や増車計画ありの比率も他の免許と比べて高く、トラックの大型化による輸送効率アップで対策を考えている事業所も存在している。
このような取り組みが行われている一方で、運輸業から荷主への要望としては、「運賃の適正化」「荷待ち時間の短縮」「運行時間帯の最適化」が上位を占めており、金銭面と時間面の両面でのさらなる状況改善を望んでいる状況がうかがえる。
————————————————–
[環境意識と次世代環境車]
エコドライブ、低燃費車両はユーザー・荷主ともにニーズあり。カーボンニュートラル対応となるハイブリッド車導入意向は、運輸業の中型トラックが2割弱で前回と同程度。
運輸業・自家用ともに実施している環境施策の上位項目は、「エコドライブの実施・管理」「最新の排出ガス規制適合車、低燃費車の使用」が挙がっており、荷主が運輸業に現在指定している環境対策でも上位に挙げられている。
環境配慮型車両の導入意向の割合は、中型ハイブリッド車が運輸業で2割弱、自家用で3割弱と前回と同程度。
だが、導入時期については、運輸業の「(導入)時期は未定」が前回49%から57%に増加したのに対し、自家用は前回63%から53%に減少しており、導入意向が高い自家用の導入時期がより具体化している。
導入の課題は、「車両価格が高い」が運輸業・自家用ともに7割弱と最も高い。「運行中に充電できる施設が少ない」「航続距離が短い」「積載可能重量が小さくなる」「積載スペースが小さくなる」も上位に挙がっており、導入時の想定用途は「中・近距離の幹線輸送用」を半数近くが想定している。
————————————————–
[安全に対する意識]
運輸業では、対面点呼や酒気帯び確認等、健康管理を中心としたドライバー管理が交通事故防止安全対策の上位に。自家用では乗務前の酒気帯び確認実施率が大幅に増加。自動運転走行機能・隊列走行については、「ドライバー不足解消」「事故の減少」効果を認識しつつも、導入意向は3割程度で前回並み。
交通事故防止安全対策は、運輸業では「乗務前の酒気帯び確認」が9割と最多で、対面点呼や健康管理を中心としたドライバー管理による安全対策も8割弱が取り組んでいる。自家用では22年4月に義務化された「乗務前の酒気帯び確認」は前回の50%からさらに上昇し、59%となった。
対面点呼や健康管理に関するIT関連機器等の今後導入(拡充)検討をみると、運輸業では点呼関連とアルコールインターロックが1〜2割で上位に挙がっているが、自家用ではアルコールインターロックが1割にとどまる。
安全サポート機器の必要性を感じたヒヤリハット事例では、「運転中の車両故障、不具合が発生した」「後方の衝突」「前方の割り込み」等、前・後方関連の事例が運輸業で4割前後と多い。
事故防止にも効果が期待される自動運転走行機能・隊列走行については、運輸業・自家用とも「ドライバー不足解消」「事故の減少」がメリットと認識される一方で、「システムの誤作動・故障」「故障・事故発生時の責任所在が曖昧」を気にしている。自動運転走行機能の導入意向は3割程度で前回並み。
————————————————–
[物流DX]
物流DX対応については、今後取り組む施策としての認識は徐々に高まりつつあるが、実際に取り組むとなると他の懸案事項が優先され、物流DXへの取り組みを身近に感じている事業所は限られている状況がうかがえる。
運輸業の輸送合理化・人材面等の施策実施状況の中で、「輸送業務関連のソフト・ハードのDX化」の取り組みは11%と下位にとどまるが、今後の予定は24%と他の項目と比べて上位に挙がっている。自家用でも、今後の予定施策で前回10%から18%に増加している。
運行管理システム・サービス関係の物流DX関連の項目をみると、運輸業では「車両位置確認」は前回同様4割弱が導入済みで最も多くなっているが、求貨求車(Webでの配車マッチングアプリ)といった他の項目は1割以下にとどまる。
荷主から運輸業に寄せられた要望に事業所が応える動きの中で、物流DX関係の項目は最も高い「荷主輸送システムへの対応」でも1割強。運輸業が荷主に協力してほしい項目でも、物流DX関係で最も高い「機械化による荷役負担軽減」は約1割にとどまっている。
以上から、物流DXを取り組むべき施策として事業所は認識し始めてはいるが、本格的に取り組むまでには至っていない状況がうかがえる。
————————————————–
(2)荷主等ヒアリング
各社では、トラックドライバー対応、事前出荷情報(ASN : Advanced Shipping Notice)や倉庫・現場管理、環境車両・カーボンニュートラル等の領域で、自社及び連携による幅広い取り組みが進められている。
今後は、こうした物流最適化の取り組みを支える各ステークホルダーにおける更なる取り組みの加速が求められる。
様々な業界の荷主等4社における2024年問題、物流DX、環境対応の取り組みについては、各企業の実状に応じた工夫・改善とともに、物流全体を広く見据えた内容となっている。
▷2024年問題については、ドライバーの労働時間、運賃改定等の対応等が着々と進められている。
リードタイム短期化・待機時間・荷役作業といった物流上の商慣行や低賃金・長時間拘束というドライバー労働環境等、これまで当然とされてきた点についての見直しが各業界・企業で積極的に推進されている。
共同輸配送における船舶・鉄道へのモーダルシフト、モーダルシフトと中継輸送の併用による長距離輸送対応等の取り組みも進んでいる。
2024年問題を背景に物流効率を指向する流れの中、トラックメーカーに対しては、荷室形状の改善、コンテナサイズの標準化、動態管理の標準装備化といった方策への要望があがっている。
▷物流DXについては、効率化・見える化等の側面からの取り組みが進んでいる。事前出荷情報(ASN:Advanced Shipping Notice)による検品レスを通じた作業時間の効率化をはじめ、検品・ピッキング等の工場・倉庫内等の作業システム・伝票管理、物流拠点や工事現場への入退場管理、動態管理等、その対応範囲は幅広いことが確認できる。
DXに対する要望として、フィジカルインターネット*1等の最新動向を踏まえたトラックメーカー側からの提案希望、自動運転化への期待の声もあがっている。
▷環境対応については、EV・FCV等の環境配慮型車両の導入が進んできている。合わせて、リチウムイオンバッテリー、太陽電池やBDF(バイオディーゼル燃料)利用、水素ステーション等の燃料面や、リトレッドタイヤ*2の利用等、車両本体に付帯する部分も取り組みがなされている。
また、工事現場への搬出入拠点の設置、DX活用による交通管理等により周辺環境改善に寄与する取り組みも行われている。
要望としては、トンクラスやダンプ等の車種面における環境対応車両種類の充実が期待されている。さらに、車両価格面、燃料・充電インフラ整備に関しては、企業単独での対応が難しく、これらに対する補助・支援施策といった行政への要望もみられる。
▷安全対策については、従前から基本的な取り組みは各社で既に実施されている中、転落防止対応、アルコール検知・ロック機能や電子ミラー等の標準装備化等による事故防止対応への要望があがっている。
各種取り組みに共通した特徴としては、自社の事業範囲にとどまらず、3PL等の物流関連企業はもとより、同業他社、異業種企業、自治体等に至るまで、幅広い関係者との協働・連携があげられる。
物流が「商流を超えた関係性の構築」の契機となり、共同体制での取り組みが進められている中、その拡大のためのさまざまな支援も必要な状況であることも確認された。
(*注)
1:インターネット通信の考え方を物流(フィジカル)に適用し、デジタル技術を駆使した新しい物流の仕組み。
2:走行により摩耗したトレッドゴム(接地部分のゴム)を張り替えて再利用するタイヤ
以上
資料
2024年度 普通トラック市場動向調査(PDF3.4MB)
https://www.jama.or.jp/library/invest_analysis/pdf/2024Trucks.pdf![]()
————————————————–
2024年度小型・軽トラック市場動向調査
————————————————–
当該調査は、小型・軽トラックユーザーの保有・購入・使用実態の変化を時系列的に把握し、今後の市場動向を探っていくことを目的としている。
また今回は、カーボンニュートラルに向けた社会の流れを受けた次世代環境車や電気自動車に対するユーザー意識の変化、燃料価格高騰やドライバー不足が及ぼす輸送への影響と対応策等、小型・軽トラック市場を取り巻く社会的な環境変化の影響、及び、小型・軽トラックに対する新しいニーズを把握すべく、以下3項目をトピックとして取り上げ、分析を行った。
– 環境配慮型車両に関する意識
– 2024年問題・物流に関する動向
– 農家におけるトラック・バン
————————————————–
調査結果の主な特徴は以下の通り
————————————————–
▷保有状況と変化の背景
小型・軽トラック・バンの保有台数は1201万台で2023年より減少。車種別では、小型トラック・軽トラックが2023年より減少。
直近2年間のトラック・バン保有台数は、運輸業で「保有減」事業所が「保有増」事業所を約1割上回る。
▷需要構造の実態
小型・軽トラック・バンの新車販売台数は、新型コロナウィルス感染拡大の影響で2020年に大きく減少。2023年まで緩やかに回復したものの、2024年は一部メーカーの認証不正問題に伴う出荷停止等が影響し再び減少。
直近2年間のトラック・バン購入率は、全体では1割で2022年度から変わらず。運輸業では1割半ばで、2022年度の約4割より大きく減少。
▷使用実態
使用パターン(仕事、私用)については、小型トラック・バンでは2018年度以降「仕事・私用兼用」とするユーザーが増加し2割。軽トラック・バンでは「仕事専用」とするユーザーが2022年度より増加し約5割。
平均月間走行距離は、仕事利用では2022年度より長距離化。私用利用では2022年度から変化なし。私用専用ユーザーの平均月間走行距離は仕事利用ユーザーの約半分。
仕事利用の運行形態は、いずれの車種も「往復型」が最も高く、特に小型トラックの<運輸業>では2022年度より増加。
私用利用での用途については、「日用品の買物(食料品・雑貨など)」に使うユーザーが約6割で最も多く、また「園芸・農作業」に使うユーザーが約4割、「通勤・通学」に使うユーザーが約3割で2022年度と同じだが、軽バン(キャブバン、ボンネットバン)は「休日型レジャー(ピクニック・ドライブ・スポーツ等)」「キャンプなどのアウトドアレジャー」に使うユーザーが2割弱まで増加している。
▷今後の購入・保有意向
次期買い替え意向車は、小型トラック・バン保有ユーザーでは「同タイプ・同クラス歩留まり」意向が最も多い。軽トラック・キャブバン保有ユーザーでも「同タイプ・同クラス歩留まり」意向が最も多いが、軽ボンバンは「他タイプ移行」の意向が最も多く5割となっている。
今後1〜2年間の保有増減の見通しをみると、運輸業では保有増の見通しをしている事業所が2022年度より減少、運輸業以外では変わらない見通しをしている事業所が9割以上となっている。
今後1〜2年間の物資輸送量の見通しをみると、運輸業以外では「増加する」が「減少する」を上回る。一方、運輸業では「増加する」が2022年度より減少し、「減少する」が「増加する」を上回る。
▷安全技術・自動運転等次世代技術に関する意識
6割弱の事業所が自動車の安全性に関心を持ち、5割半ばの事業所が購入時に安全性を重視している。従業員規模が大きい事業所ほど、安全性への関心が高い。
有償でも装着したい先進安全技術では「衝突被害軽減ブレーキ」「歩行者の探知・保護支援システム」「誤発進防止システム」が上位にあがり、運輸業では「ドライバー異常警報システム」も上位にあがる。
自動運転に対する意識では、全体では自動運転車の導入意向事業所は2割弱だが、従業員規模別でみると30人以上の事業所では3割を超える。
自動運転技術に期待する事業所は、全体では6割強で、従業員規模別でみると300人以上の事業所では約9割に達しており、具体的には「ドライバーの負担が軽減」や「安全性が高まる」技術を望む声が上位にあがる。
▷環境配慮型車両に関する意識
月々の燃料代の負担感では、「負担を感じている(非常に+やや)」事業所が8割。環境問題に関する考え方でも「多少価格が上がっても低燃費の車を選ぶ」「環境への影響を考え荷下ろしの時にアイドリングをやめる」「省資源を意識し燃費効率の良い経済速度で走るようにする」が上位にあがる。
また、次世代環境車に対する購入意向については、すべての車種において「ハイブリッド車」が最も高く、次世代環境車の導入検討理由として「燃料価格変動の影響を受けにくくなる」が上位にあがる一方、懸念点は「車両価格が高い」が最も高い。
電気自動車(EV)の導入については、補助金が「無くても検討する」事業所は2%にとどまり、補助金が「50万円まで」だと検討する事業所が2割半ば、「50万円超~100万円」だと検討する事業所が3割弱となる一方で、「いくら補助金があっても検討しない」事業所も3割半ばとなっている。
電気自動車(EV)超小型モビリティは5割半ばの事業所が認知しており、3割が購入や導入、利用を検討。「小回りが効いて便利」「駐車スペースが小さい」「運転のしやすさ」などサイズや取り回しに対する期待が高い。
電気自動車(EV)小型トラックの積載量減については3割強が認知、4割が購入に影響あり。
▷安全意識と先進安全技術
自動車の安全性に約8割の事業所が関心あり。運輸業では購入時重視が約8割と18年度調査から増加。有償装着意向は「衝突被害軽減ブレーキ」「歩行者の検知・保護支援システム」「誤発進防止システム」が高い。事業所調査において、自動運転技術への期待度・導入意向ともに18年度より増加。
▷2024年問題・物流に関する動向
2024年問題の影響は、全体では「ドライバーの採用が難航」「車両の買い替えや増車」「事業所の売上、利益の減少」「ドライバーの収入減少」が上位にあがり、運輸業では「事業所の売上、利益の減少」「ドライバーの拘束時間の減少による供給力不足」「ドライバーの採用が難航」が上位にあがる。なお、運輸業以外よりも運輸業の方が影響は大きい。
物流革新に向けた政策パッケージの認知・取り組み状況は、「商慣行の見直し」「物流の効率化」「荷主・消費者の行動変容」のそれぞれについて、全体では5割以上、運輸業では7割以上の事業所が認知しているが、「いずれも知っていて、すでに取り組んでいる」事業所は、全体では1割以下、運輸業では2割以下。
現在の事業所における運転手の確保状況は、全体では「不足(かなり+やや)」が3割強、運輸業では6割弱となっており運輸業の方が高い。
また、運転手不足の困窮度についても、全体では「困っている(非常に+やや)」が約2割だが、運輸業では約5割となっており運輸業の方が高い。従業員規模別でみると、従業員規模が大きくなるほど困窮している割合が増加。
▷農家におけるトラック・バン
販売農家数の減少は続いており、農業の継続意向についても「廃業予定」とする農家が2016年度の1割強より2024年度は2割強に増加。
主運転者の年代別で農業の継続意向をみると、50代以下は「規模を拡大・会社運営予定」が4割半ばと最も高いが、70代以上は「規模を縮小して継続+廃業予定」が約5割と半数を占める。
農家の保有車種では、「軽トラック」とする農家が9割を占める状況は2016年度から変わらない。主運転者の年代では「70代以上」が約5割と半数を占めており、2022年度の3割半ばより上昇した。
報告書は下記自工会WEBサイトに掲載している。
http://www.jama.or.jp/library/invest_analysis/![]()
以下参考
2024年度小型・軽トラック市場調査の概要
————————————————–
1.調査実施概要(2024年度調査)
————————————————–
▷事業所調査
調査手法:訪問留置調査法
調査地域:東京都周辺50キロ圏および大阪市・名古屋市周辺各30キロ圏
調査対象:従業員数5人以上の事業所(小型・軽トラックの保有・非保有を含む)
母集団:令和3年度経済センサスの東京都・愛知県・大阪府の事業所数
有効回収数:609サンプル
調査実施期間:2024年8月9日(金)~10月4日(金)
▷ユーザー調査
調査手法:訪問留置調査法
調査地域: 全国
調査対象:小型・軽トラック保有ユーザー
母集団:全国の小型・軽トラック保有ユーザー
有効回収数:1,015サンプル
調査実施期間:2024年8月9日(金)~10月4日(金)
▷WEB調査
調査手法:WEB調査法
調査地域: 全国
調査対象:小型・軽トラック保有事業者
母集団:令和3年度経済センサスの全国の事業所数にスクリーニング調査の小型・軽トラック保有率をかけて算出
有効回収数:897サンプル
調査実施期間:2024年9月13日(金)~9月18日(水)
————————————————–
2.調査結果概要
————————————————–
▷[総括]
小型・軽トラック・バンの保有台数については2023年より減少し、車種別で減少しているのは小型トラック、軽トラックとなっている。
トラック・バンの直近2年間の購入/リースの状況については、全体では「購入/リース(新車+中古)」したユーザーは1割で2022年度から変わらず、運輸業では1割半ばで2022年度の約4割から大きく減少している。
また、運輸業では今後1〜2年間の物資輸送量を「増加する」と見通す事業所が2022年度から減少し、今後1〜2年間のトラック・バン保有台数を「増加する」と見通す事業所も2022年度から減少している。
自動車の安全性に6割弱が関心を持っており、従業員規模が大きいほど高い。
また、購入時に5割半ばの事業所が安全性を重視している。有償でも装着意向が高い先進安全技術は「衝突被害軽減ブレーキ」「歩行者の探知・保護支援システム」「誤発進防止システム」。自動運転車の導入意向がある事業所は2割弱だが、自動運転技術に期待する事業所は6割強で、「ドライバーの負担が軽減される」「安全性が高まる」への期待が高い。
次世代環境車の導入ではすべての車種で「ハイブリッド車」の意向が最も高く、導入検討理由は「燃料価格変動の影響を受けにくくなる」が高い一方、懸念点としては「車両価格が高い」が最も高い。
電気自動車(EV)超小型モビリティは5割半ばの事業所が認知しており、3割が購入や導入、利用を検討。小回りが効いて便利、駐車スペースの小ささ、運転のしやすさなどサイズや取り回しに対する期待が高い。
2024年問題の影響としては、運輸業では「事業所の売上、利益の減少」「ドライバーの拘束時間の減少による供給力不足」「ドライバーの採用が難航」が上位。
運輸業は運輸業以外と比較し影響が大きい。また、「物流革新に向けた政策パッケージ」のすべてを認知し、すでに取り組んでいる事業所は全体では1割弱、運輸業では2割弱。
1)時系列分析
[保有状況と変化の背景]
小型・軽トラック・バンの保有台数は1201万台で2023年より減少。車種別では、小型トラック・軽トラックが2023年より減少。
直近2年間のトラック・バン保有台数は、運輸業で「保有減」事業所が「保有増」事業所を約1割上回る。
<保有変化の背景>
保有台数が減少した理由としては、「経費を節約するため」「これまで保有過多だったため」「従業員が減ったため」「輸送量が減ったため」が上位にあがる。
直近2年間で保有台数が減少した社会的背景については、「全体的な景気の影響」「高齢化社会の進展・労働力不足」「ガソリンなどの燃料価格の高騰」が上位にあがる。
直近2年間の物資輸送量は、全体では「増えている」が2022年度より増加するも、運輸業では「減っている」が「増えている」を上回る。
なお、運輸業における稼働率低下の理由としては、「全体の運輸量が減ったため」「運転手が不足しているため」が上位にあがり、運転手不足の困窮度は2022年度より増加し、約7割の事業所が困窮している。
[需要構造の実態]
小型・軽トラック・バンの新車販売台数は、新型コロナウィルス感染拡大の影響で2020年に大きく減少。2023年まで緩やかに回復したものの、2024年は一部メーカーの認証不正問題に伴う出荷停止等が影響し再び減少。
直近2年間のトラック・バン購入率は、全体では1割で2022年度から変わらず。運輸業では1割半ばで、2022年度の約4割より大きく減少。
<需要動向の背景>
小型トラック・バンは同型車への代替が増加し、軽トラック・バンはすべて歩留り。直近2年間で買い替えた車(新車)の購入時期については、予定より「遅らせた」が「早めた」を上回る。トラック・バンを保有する事業所における買い替えについての意見は、「まだ使えるうちに買い替えるのはもったいない」「できるだけ長く使った方が経済的だと思う」との意見が7割以上。なお、運輸業では「できるだけ長く使った方が経済的だと思う」が8割で最も高く、2018年度から増加が続く。
[使用実態]
使用パターン(仕事、私用)については、小型トラック・バンでは2018年度以降「仕事・私用兼用」とするユーザーが増加し2割。軽トラック・バンでは「仕事専用」とするユーザーが2022年度より増加し約5割。
平均月間走行距離は、仕事利用では2022年度より長距離化。私用利用では2022年度から変化なし。私用専用ユーザーの平均月間走行距離は仕事利用ユーザーの約半分。
仕事利用の運行形態は、いずれの車種も「往復型」が最も高く、特に小型トラックの<運輸業>では2022年度より増加。
私用利用での用途については、「日用品の買物(食料品・雑貨など)」に使うユーザーが約6割で最も多く、また「園芸・農作業」に使うユーザーが約4割、「通勤・通学」に使うユーザーが約3割で2022年度と同じだが、軽バン(キャブバン、ボンネットバン)は「休日型レジャー(ピクニック・ドライブ・スポーツ等)」「キャンプなどのアウトドアレジャー」に使うユーザーが2割弱まで増加している。
[今後の購入・保有意向]
次期買い替え意向車は、小型トラック・バン保有ユーザーでは「同タイプ・同クラス歩留まり」意向が最も多い。軽トラック・キャブバン保有ユーザーでも「同タイプ・同クラス歩留まり」意向が最も多いが、軽ボンバンは「他タイプ移行」の意向が最も多く5割となっている。
今後1〜2年間の保有増減の見通しをみると、運輸業では保有増の見通しをしている事業所が2022年度より減少、運輸業以外では変わらない見通しをしている事業所が9割以上となっている。
今後1〜2年間の物資輸送量の見通しをみると、運輸業以外では「増加する」が「減少する」を上回る。一方、運輸業では「増加する」が2022年度より減少し、「減少する」が「増加する」を上回る。
2)トピックス分析
[安全技術・自動運転等次世代技術に関する意識]
6割弱の事業所が自動車の安全性に関心を持ち、5割半ばの事業所が購入時に安全性を重視している。従業員規模が大きい事業所ほど、安全性への関心が高い。
有償でも装着したい先進安全技術では「衝突被害軽減ブレーキ」「歩行者の探知・保護支援システム」「誤発進防止システム」が上位にあがり、運輸業では「ドライバー異常警報システム」も上位にあがる。
自動運転に対する意識では、全体では自動運転車の導入意向事業所は2割弱だが、従業員規模別でみると30人以上の事業所では3割を超える。
自動運転技術に期待する事業所は、全体では6割強で、従業員規模別でみると300人以上の事業所では約9割に達しており、具体的には「ドライバーの負担が軽減」や「安全性が高まる」技術を望む声が上位にあがる。
[環境配慮型車両に関する意識]
月々の燃料代の負担感では、「負担を感じている(非常に+やや)」事業所が8割。環境問題に関する考え方でも「多少価格が上がっても低燃費の車を選ぶ」「環境への影響を考え荷下ろしの時にアイドリングをやめる」「省資源を意識し燃費効率の良い経済速度で走るようにする」が上位にあがる。
また、次世代環境車に対する購入意向については、すべての車種において「ハイブリッド車」が最も高く、次世代環境車の導入検討理由として「燃料価格変動の影響を受けにくくなる」が上位にあがる一方、懸念点は「車両価格が高い」が最も高い。
電気自動車(EV)の導入については、補助金が「無くても検討する」事業所は2%にとどまり、補助金が「50万円まで」だと検討する事業所が2割半ば、「50万円超~100万円」だと検討する事業所が3割弱となる一方で、「いくら補助金があっても検討しない」事業所も3割半ばとなっている。
電気自動車(EV)超小型モビリティは5割半ばの事業所が認知しており、3割が購入や導入、利用を検討。「小回りが効いて便利」「駐車スペースが小さい」「運転のしやすさ」などサイズや取り回しに対する期待が高い。
電気自動車(EV)小型トラックの積載量減については 3割強が認知、4割が購入に影響あり。
[2024年問題・物流に関する動向]
2024年問題の影響は、全体では「ドライバーの採用が難航」「車両の買い替えや増車」「事業所の売上、利益の減少」「ドライバーの収入減少」が上位にあがり、運輸業では「事業所の売上、利益の減少」「ドライバーの拘束時間の減少による供給力不足」「ドライバーの採用が難航」が上位にあがる。なお、運輸業以外よりも運輸業の方が影響は大きい。
物流革新に向けた政策パッケージの認知・取り組み状況は、「商慣行の見直し」「物流の効率化」「荷主・消費者の行動変容」のそれぞれについて、全体では5割以上、運輸業では7割以上の事業所が認知しているが、「いずれも知っていて、すでに取り組んでいる」事業所は、全体では1割以下、運輸業では2割以下。
現在の事業所における運転手の確保状況は、全体では「不足(かなり+やや)」が3割強、運輸業では6割弱となっており運輸業の方が高い。また、運転手不足の困窮度についても、全体では「困っている(非常に+やや)」が約2割だが、運輸業では約5割となっており運輸業の方が高い。従業員規模別でみると、従業員規模が大きくなるほど困窮している割合が増加。
[農家におけるトラック・バン]
販売農家数の減少は続いており、農業の継続意向についても「廃業予定」とする農家が2016年度の1割強より2024年度は2割強に増加。
主運転者の年代別で農業の継続意向をみると、50代以下は「規模を拡大・会社運営予定」が4割半ばと最も高いが、70代以上は「規模を縮小して継続+廃業予定」が約5割と半数を占める。
農家の保有車種では、「軽トラック」とする農家が9割を占める状況は2016年度から変わらない。主運転者の年代では「70代以上」が約5割と半数を占めており、2022年度の3割半ばより上昇した。
以上
資料
2024年度小型・軽トラック市場動向調査(PDF3.6MB)
https://www.jama.or.jp/library/invest_analysis/pdf/2024LightTrucks.pdf![]()